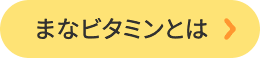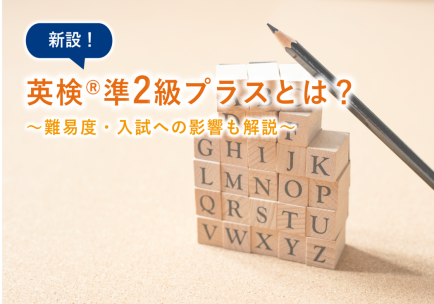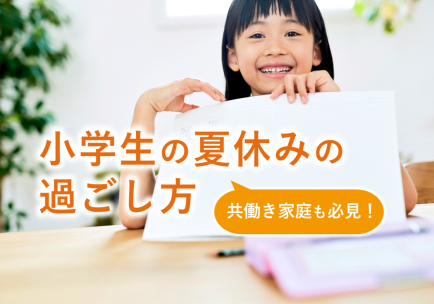不登校のお子さまは年々増え続ける傾向にあるため、一体何が原因なのか、どうサポートをしたらよいのかと迷う保護者さまも多いことでしょう。
この記事では、お子さまの不登校の原因にはどのようなものがあるのか、またもしもお子さまが不登校になったときに保護者さまがどんなサポートができるかをお伝えします。不登校の際に利用できる学習サポートの具体例もご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
不登校の現状

まずは不登校の現状について簡単に確認しておきましょう。
そもそも、わが子が登校しなくなったとき、多くの保護者さまが「うちの子は不登校なのだろうか」と不安に感じることと思います。ここで押さえておきたいのが、不登校の定義です。
1992年の学校不適応対策調査研究協力者会議では、不登校を次のように位置づけています。
「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にあること(ただし、病気や経済的な理由によるものを除く)をいう。」※引用
また1998年には、上記の内容に加えて、「年間30日以上の欠席があること」が不登校の定義に加わりました。なお「不登校」という言葉が用いられるようになったのは1999年以降のことで、それ以前は「学校ぎらい」あるいは「登校拒否」などの言葉で表現されていました。現在では「登校したくても、できない」という子どもたちも多いことがわかり、「登校拒否」という言葉は使われなくなっています。
※引用:第3章 不登校|国立教育政策研究所
不登校の児童・生徒は年々増えている
不登校に該当する子どもの数は、小学生、中学生共に増加傾向にあります。2024年に文部科学省がまとめたデータによると、不登校児童生徒数は34万6482人で、11年連続の増加となりました。(※1)さらに増加率は前年比で15.9%と、大変早いペースであることがわかります。
このように不登校の生徒数が増加しており、お子さまの不登校に悩む保護者さまも同じように増加しているのです。
お子さまがたびたび学校を休みたいと言い出したり、何日も休んで登校しなかったりすると、罪悪感や無力感をお持ちになる保護者さまも多くいらっしゃるようです。しかし今や不登校は、少数のご家庭だけの特殊な悩みではありません。保護者さまやお子さまが、少しでも気持ちを楽に不登校期間を乗り越えるために、まずは不登校の原因を把握することが大切です。
※1 参考:令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要|文部科学省
不登校の主な原因

不登校にはさまざまな原因があります。ここでは不登校の原因となりうる内容をケース別に解説します。
不登校の原因は多種多様で、特定できない可能性もあります。不登校の原因をさぐることは、対策や対応方法を考慮するためのものであって「犯人探し」ではないことを念頭に置きつつ、どのような原因があるかを見ていきましょう。
学校生活が起因となるケース

よくあるのは、学校生活そのものが不登校の原因となっているケースです。毎日通う場所であるだけに、少しでも困難を感じた場合に不登校に至りやすいといえるでしょう。
ケース①勉強がわからない、授業についていけない
授業についていけない、成績が上がらない、といった勉強に関連する悩みから、自信を失い、やがて学校に行くこと自体が苦痛に感じられてしまうケースがあります。
例えば小学校の3年生~4年生は、学習の難易度が大幅に上がり、学習範囲が増えるタイミングです。子どもには難易度が上がっている感覚がなく、低学年と同じ感覚で学習をしているうちに授業についていけなくなってしまうことはよくあります。
このほか、授業で先生に当てられたときに答えられなかった、そのときの先生や友だちの反応が本人にとって好ましくなかった、などさまざまな原因が考えられるでしょう。
ケース②先生との関係や相性が良くない
お子さまが先生との間に壁を感じている場合、不登校につながってしまうことがあります。
先生は、指導方針も立ち居振る舞いも人それぞれです。よくみられるケースは、先生の指導方針が厳しくお子さまが萎縮してしまう、言葉づかいや語気にお子さまから見て冷たさがあり怖く感じられてしまう、などでしょう。なかには先生の声が大きく、元気がよいために、お子さまが自分を否定されているように感じることもあります。
ただし、先生とのコミュニケーションにズレが生じて不登校に至っているケースでは、年度が変わり担任の先生が交代することで、不登校が解消するケースもみられます。
ケース③子ども同士での人間関係トラブルがある
子ども同士のもめ事やけんかやいじめは、多くの児童・生徒が集まる学校では起こりうることです。しかしそれでも、不和が根深いものになってしまうと「あの子がいるから、学校へ行きたくない」という感情につながる可能性があるでしょう。
もちろん、人間関係トラブルがイジメにまで発展していないかどうかは、注視している保護者さまも多い部分かと思います。身体的な嫌がらせはもちろん、言葉の暴力、SNSを使った学校外でのトラブルなども、不登校の原因になりえます。
ケース④学校の環境になじめない
お子さまの性格や感じ方、特性から、学校での集団行動を苦手に感じてしまうケースがあります。また直前まで学校に通っていたのに、転校や進学などで新しい環境になじめなかった、ということも珍しくありません。お子さまの心の状態が学校の状況や雰囲気にうまく合わない場合に、不登校につながる可能性があります。
家庭環境が影響しているケース
不登校の要因が家庭環境に潜んでいるケースもあります。家庭の様子で次のようなことがないか考えてみましょう。
ケース①家庭内のコミュニケーションが不足している
家庭内でコミュニケーションが不足し、お子さまの心情を保護者さまがうまく聞いてあげられないと、お子さまは、寂しさや不安を不登校という形で表出させることがあります。
短時間でも毎日のように会話ができているか、家事の手を止めて話を聞いてあげる時間があるか、ぜひ振り返ってみてください。
ケース②保護者が仕事と家庭のバランスをうまくとれていない
お仕事をされている保護者さまは、仕事と家庭に、バランスよく意識を振り分けられているかを確認してみましょう。特に、不規則勤務や長時間勤務はバランスが崩れがちです。
ウエイトが仕事に大きく傾き家にいる時間がほとんどない場合、お子さまと対面で過ごす時間も必然的に短くなっていると考えられます。こうした状態が家庭内でのコミュニケーション不足を招き、不登校へつながってしまうこともあります。
心身の不調が起因となるケース
将来への不安、自己肯定感・自己効力感の低さといったことが原因で、無気力な状態になってしまうことがあります。学校に行く意味が見いだせなくなり、足が学校へ向かず不登校につながるケースです。
実は、不登校の原因として最も多いのが「無気力・不安」です。例えば令和6年3月に公表された文部科学省委託事業による『不登校の要因分析に関する調査研究 報告書』でも、不登校の原因についてアンケートをとった結果「不安・抑うつの訴え」という回答が最多となっています。
大人の側は、ばくぜんとしている、気のせいではないか……などと軽く見ずに、お子さまの心のつらさを日頃から受け止めることが大切です。
これとは全く別で、成長期特有の身体の不調から登校できなくなるケースもあります。代表的なものが起立性調節障害です。
起立性調節障害は、自律神経の乱れによって立ち上がった時などに脳や体への血流が低下してしまう病気で、思春期のお子さまに多く見られます。
お子さまの体調が悪かったり、登校できなかったりすると不安になると思いますが、お子さまを責めることのないようにしましょう。保護者さまもひとりで抱え込まず、学校や適切な機関とつながって、周囲に相談をしながらお子さまをサポートしてあげることが大切です。
※2 参考:文部科学省委託事業 不登校の要因分析に関する調査研究 報告書|文部科学省
不登校に関して親ができるサポート

お子さまの不登校に際して、親ができるサポートはたくさんあります。保護者さまのサポートによって学校へ戻る切っ掛けを見つけたり、新たな自分の道を見つけたりするお子さまは多いのです。
ここまで、さまざまな不登校の原因をみてきましたが、原因がわかれば不登校が解決するとは限りません。また明確な原因がないことも、複数の原因が絡み合っていることもあります。原因究明だけに力を注ぐのではなく、あたたかく見守りながらサポートをしてあげるとよいでしょう。
不登校の子どもに理解を示す
不登校のサポートで大切なのは、お子さまの気持ちに寄り添い、理解を示すことです。
不登校のお子さまは、登校できないことに罪悪感をもったり、自信を喪失したりしていることがほとんどです。早く学校に復帰しなければと焦ってしまうお気持ちはありつつも、あくまでもお子さまのペースで、ゆっくりとサポートを続けていくことが大切です。
子どもの行動や考えを否定せずゆっくりと回復を待つ
まず何よりも、お子さまの行動や考えを頭ごなしに否定することなく、本人が一番辛いということを理解し、共感してあげましょう。
お子さまが不安を感じていたり、孤独感や自己否定感といったネガティブな感情をもっていたりすると、つい叱りたくなってしまうことも多いと思いますが、叱ることで不登校は解決しません。またここで叱ってしまうとお子さまが心を閉ざしてしまうことも。
大切なのは、お子さまに「家は安全な場所だ」「保護者は自分の理解者だ」と感じ、安心してもらうことです。「学校へ行きなさい」などとプレッシャーを決して与えず、家で過ごすことを認めてあげましょう。このときお子さまがしっかりと安心感を得られれば、それが次の一歩を踏み出すエネルギーの源となります。
学習面で必要なサポートを行う
不登校の原因により、保護者にできるサポートは異なります。いくつかの例をご紹介します。
不登校で保護者さまが心配されることの一つが、学習の遅れです。気になるあまり「学校へ行かないのなら、家で勉強をしなさい」と指導するケースもありますが、これは逆効果になりかねずおすすめできません。
最初はしっかりと休ませてあげて、時間が経過してから無理のない範囲で教材をそろえる、お子さまの興味ある分野から取り組ませて、お子さまにペースを合わせながら学習習慣を取り戻す、といった方法がよいでしょう。
学習が可能な状態になったら、個別指導塾で学習リズムを身につけるのもおすすめです。
学校との連携を欠かさない
担任の先生や学校の担当者などと定期的に連絡を取り、お子さまの様子を共有しましょう。スクールカウンセラーがいる場合は、相談するとサポートを受けられます。お子さまだけではなく、保護者がスクールカウンセラーにカウンセリングを受けられる学校もあります。
学校生活への復帰が視野に入れられる場合は、担任の先生と相談しながら積極的に連携していくことが必要です。
一方、学校には登校せず、学校外の公的機関や民間施設へ通うことで、出席扱いにしてもらえる制度もあります。出席扱いにできる施設は、教育委員会等が設置する公的機関、もしくは学校長が適切と判断した民間施設に限られる点に注意が必要です。さらに、学校と保護者および施設側で十分に連携が取れている等、いくつかの条件もあるので、学校へ問い合わせてみましょう。
なお、出席扱い制度の利用をサポートできる塾もあります。出席扱い制度について詳しく説明してくれたり、学校との交渉を一緒に行ってくれたりするため、お子さまも保護者様も安心です。通塾を出席扱いにできる場合もあるので、まずは相談してみるのがおすすめです。
生活リズムを整える
不登校のお子さまは生活リズムが崩れがちですが、生活リズムが整わなければ登校に対する心理的なハードルが高くなってしまいます。ここでは、生活リズムを整える方法を解説します。
朝のルーティンを確立する
朝のルーティンは、生活リズム全体を安定させるという効果をもっています。まずは決まった時間に起床し、日光を浴びましょう。その後、朝食を摂る、身支度を調える、といったルーティンを毎日繰り返すようにします。
不登校の場合、朝、決まった時間に起床することが難しくなるケースが多くみられます。起立性調節障害など病気の場合を除き、まずは朝、起きることを目指しましょう。
適切な睡眠時間を確保する
朝に起きられない原因の一つに、夜更かしがあります。起床時間を考えて早めに就寝し、適切な睡眠時間を確保しましょう。
就寝時間をコントロールするには、就寝前のルーティンや就寝時間を決めるのも効果的です。思春期のお子さまは、寝るのがつい遅くなりがち。心身の健康と睡眠時間、また寝る前の過ごし方などを保護者さまとゆっくり話し合うことで、生活パターンを変えられる可能性があります。
食生活の改善に努める
栄養バランスの取れた食事を、規則正しく決まった時間に摂ることをおすすめします。
食事の栄養バランスが取れていることは、心身のさまざまな不調を改善に導く切っ掛けとなります。よい栄養バランスは、よい腸内環境にも必要です。
栄養不足の状態や、腸内環境が良くない状態は、体調の悪化や気力の低下を招く可能性があるともいわれています。不登校で乱れがちな心身を整えるため、お子さまの食生活に気を配りましょう。
不登校の子どもが学校以外で学習支援を受けられる場所

不登校の場合、学校以外でも学習支援を受けられる場所があるため、活用を前向きに検討してみましょう。具体的にどのような学習支援があるかを解説します。
塾・家庭教師
塾や家庭教師を利用すると、学校で授業を受けられない分の学習サポートを全面的に任せることができます。
塾にもさまざまなものがありますが、不登校の場合に特におすすめできるのが個別指導塾です。個別指導塾ではお子さまと講師が対話しながら授業を行うため、お子さまのペースで学習を進められます。一律のカリキュラムで進められる集団塾に比べて、学習の遅れにも対応しやすいでしょう。好きな・得意な教科・科目から始めることもできるので、学習に対する自信をつけることもできます。
また不登校のお子さまの場合、集団塾は周りの目線が気になるため、個別指導塾のほうが気楽に通える、というケースもあります。
東京個別・関西個別ではお子さまそれぞれの性格やご状況に合わせた最適な学習プランの作成が可能で、不登校でも学習の遅れを取り戻しやすいのが特徴です。また講師が寄り添って伴走することで気力を取り戻し、将来の夢や目標を見つけられるお子さまも多くいらっしゃいます。
進学についてもたくさんの学校情報が蓄積されているため、お子さまに合った学校が見つかりやすく、進学の実績も豊富です。個別指導塾でのサポートをご検討の際は、東京個別・関西個別へ問い合わせてみてはいかがでしょうか。
フリースクール
フリースクールは、自由なスタイルでの学習が可能な教育機関です。単に勉強をする場所というだけではなく、子どもの居場所としての役割も果たすことがあります。
個性を尊重する環境下で興味のある分野を学んだり、体験活動で仲間を作ったりもできるでしょう。一方で多くのフリースクールでは学習における難易度の目安を基礎レベルあるいは標準レベルとしているため、物足りないと感じるお子さまや、保護者さまもいます。
オンライン学習
現在、学校が不登校の子ども向けにオンライン学習を取り入れ、学習支援を行う例が見られ始めています。オンラインで配信される授業を受け、クラスの子どもたちとも交流をもつことができますが、実際にはこうした取り組みを行う学校はまだ少なく、利用できるお子さまは少ないでしょう。
学校で実施されているものとは別に、フリースクールがバーチャル教室やメタバース空間を活用したオンライン学習を提供しているケースもあります。オンラインゲームを利用して互いの交流を図る取り組みなどもあり、楽しみながらコミュニケーション能力を育みたい方などに人気です。
地域や行政の支援
不登校のお子さまに対しては、各自治体が教育支援センターを設置して学習支援などを行い、学校への復帰をサポートしています。このほか、フリースクール利用に対する補助やカウンセリング利用支援など、地域によって違うもののさまざまな支援があるため、問い合わせてみるとよいでしょう。
不登校の原因にとらわれずお子さまの不安に寄り添った対応を
不登校に至る原因はお子さまによってさまざまですが、どのお子さまも、自分自身の日常や学校に対して悩みや不安をもっていることは共通しています。不登校をサポートする際はお子さまの不安に寄り添い、かつお子さまの意思を尊重した形で、学習やメンタル、生活を支えていくことが大切です。
しかし、すべてをご家庭だけで支える必要はありません。保護者さまだけで悩まずに、まわりの支援を利用しましょう。勉強や進路のことなら、東京個別・関西個別に相談してはいかがでしょうか。
東京個別・関西個別では、お子さまのペースを重視した学習サポートを提供しております。お子さまの性格やお気持ち、学力などの現状に寄り添い、安心感を持てる環境を大切にしているため、不登校でも着実に学習を進め、自信や学力の遅れを取り戻すことが可能です。
見学や相談会も個別なので、まわりを気にせず質問できます。カリキュラム、通塾ペース、学び方など、お子さまに合った対応ができるか相談してみるとよいでしょう。
東京個別・関西個別では、不登校の際にも確かな指導力で、お子さま・保護者さまの学習や進学に関する不安に寄り添います。
不登校で心配な学力面も個別指導で徹底サポート
お子さまのペースや現状に合わせて学習を進められ、豊富な学校情報で進学もサポート可能です。不登校でお子さまの学力が心配、進学先が見つかるか不安、という場合はお気軽にご相談ください。